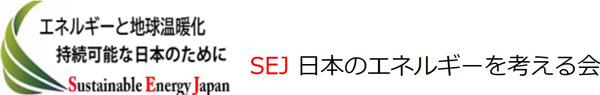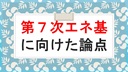 1. はじめに
1. はじめに 第7次エネルギー基本計画改定作業のため、経産省の総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会での議論が5月から開始されている。エネルギーを取り巻く世界情勢は大きく変化しつつあるなかで、日本のエネルギー安全保障を確保していくうえで激動期であるとの危機感を共有し、想定される諸変化に対応し得る現実を考慮したバランスのとれた計画策定が求められている。一方、GX実行会議においてもエネルギー安定供給、経済成長、脱炭素の同時達成を目指してGX2040年ビジョンの策定に向けた作業が開始されている。
 1. はじめに 日本原子力学会教育委員会では、平成8年(1996年)より、教科書調査ワーキンググループを設置して、小学校、中学校、及び高等学校の教科書における原子力・放射線関連の記述の調査を実施してきた。本調査活動の概要について以下に述べる。
1. はじめに 日本原子力学会教育委員会では、平成8年(1996年)より、教科書調査ワーキンググループを設置して、小学校、中学校、及び高等学校の教科書における原子力・放射線関連の記述の調査を実施してきた。本調査活動の概要について以下に述べる。
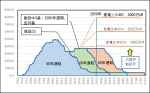 概要
概要岸田総理が主導したGX実行会議では、2050年以降の脱炭素社会を構築し維持するためには、「原子力を可能な限り活用する」ことが不可欠とされた。
2050年の電力需要は2030年の約1.5倍と見込まれ、発電量を増大する必要がある。「原子力を可能な限り活用する」のに必要な新増設炉の建設期間を考えると今直ちに着手する必要があるが、そのような状況は見られない。
SEJだより第37号 日本の産業の衰退を食い止めなくてはならない ―原子力ばかりでない周回遅れをどうするかー湯之上隆著「半導体有事」を読んで
- カテゴリ: 原子力政策 2023-12-9 9:45 閲覧 (734)

はじめに
近年、日本の数々の産業はピーク・アウトを経験し、世界的シェアの低下、産業の衰退に陥っている。電気製品に限っても、テレビ、ビデオ、から始まり産業の米といわれる半導体までもシェアが低下している。その原因を探る本も多く出版されているが、今年4月に出版された著者湯之上氏の「半導体有事」の分析についてポイントをまとめてみた。(半導体有事: 著者 湯之上隆 2023年4月初版 文春新書)加えて、最後に、原子力にも共通する解決すべき課題について考えてみたい。

1.まえがき
日本になにゆえ高速増殖炉が必要なのかについて改めて思い起こしてみたい。言うまでもなく日本は、必要とするエネルギーの殆どを海外から輸入している。それに加えウクライナ戦争など日本を取り巻くエネルギー情勢は厳しさを増している。日本にエネルギー危機が再来した時に想定される尋常でない事態については過去の歴史を振り返れば明らかである。

1.まえがき
終戦後間もなく、1953年アイゼンハワー大統領の国連演説、Atoms For Peace により世界が協力して原子力の平和利用を進めるとともに核管理を通じて核拡散防止を図ることが提唱された。日 本はこれを受けて原子力開発のための予算2.5億円を補正予算で計上するとともに原子力委員会の創設や関係法整備を図った。1956年には原子力委員会が原子力長計をとりまとめ、核燃料サイクルを確立するため高速増殖炉、燃料再処理の技術開発とともに原子燃料の自給体制の確立を目指す方針が示された。
 1.まえがきSEJだより第32号で指摘した通り、傷んだ日本の原子力発電を復活させるためには、これまでのやり方を現実を踏まえたものに見直すことが必要である。現状を認識するとともに、どのように変革、改革をすることによって原子力発電が再び日本の主幹電源となり得るのか、検討を行ったので、ここにその成果を含め提言を行いたい。
1.まえがきSEJだより第32号で指摘した通り、傷んだ日本の原子力発電を復活させるためには、これまでのやり方を現実を踏まえたものに見直すことが必要である。現状を認識するとともに、どのように変革、改革をすることによって原子力発電が再び日本の主幹電源となり得るのか、検討を行ったので、ここにその成果を含め提言を行いたい。

1.まえがき
政府はこれまでの原子力政策の見直しを行ない、原子力エネルギーの活用が日本にとって必要かつ重要であることを明確化し政策を転換した。
これは、福島第一事故後の原子力政策の大転換で高く評価されるものであるが、首相と政府が方針を打ち出しただけで、福島事故後の12年間で傷んだ日本の原子力界の回復と活性化が自動的に達成できるものではない。本報では、日本の原子力の現状と対策について「日本のエネルギーを考える会」の会員が議論した結果について記し読者の評価を待ちたい。
 我が国の原発は東日本大震災(以下震災)以前にはBWRを含め54基が稼働していた。現在10基のみが再稼働しているに過ぎない。 再稼働しているのはPWRのみであるが、震災前に稼働していた24基のうち、震災以降8基が廃炉となり、現時点で新規制基準の審査を受けているものが4基、設置変更の許可を受けたものが2基である。詳細は図1「原子力発電所の現状」をご覧いただきたい。このような状況の中でも原子力のサプライヤーは将来に向けた戦略を立てている。そこでサプライヤーの取り組みを調べてみた。
我が国の原発は東日本大震災(以下震災)以前にはBWRを含め54基が稼働していた。現在10基のみが再稼働しているに過ぎない。 再稼働しているのはPWRのみであるが、震災前に稼働していた24基のうち、震災以降8基が廃炉となり、現時点で新規制基準の審査を受けているものが4基、設置変更の許可を受けたものが2基である。詳細は図1「原子力発電所の現状」をご覧いただきたい。このような状況の中でも原子力のサプライヤーは将来に向けた戦略を立てている。そこでサプライヤーの取り組みを調べてみた。