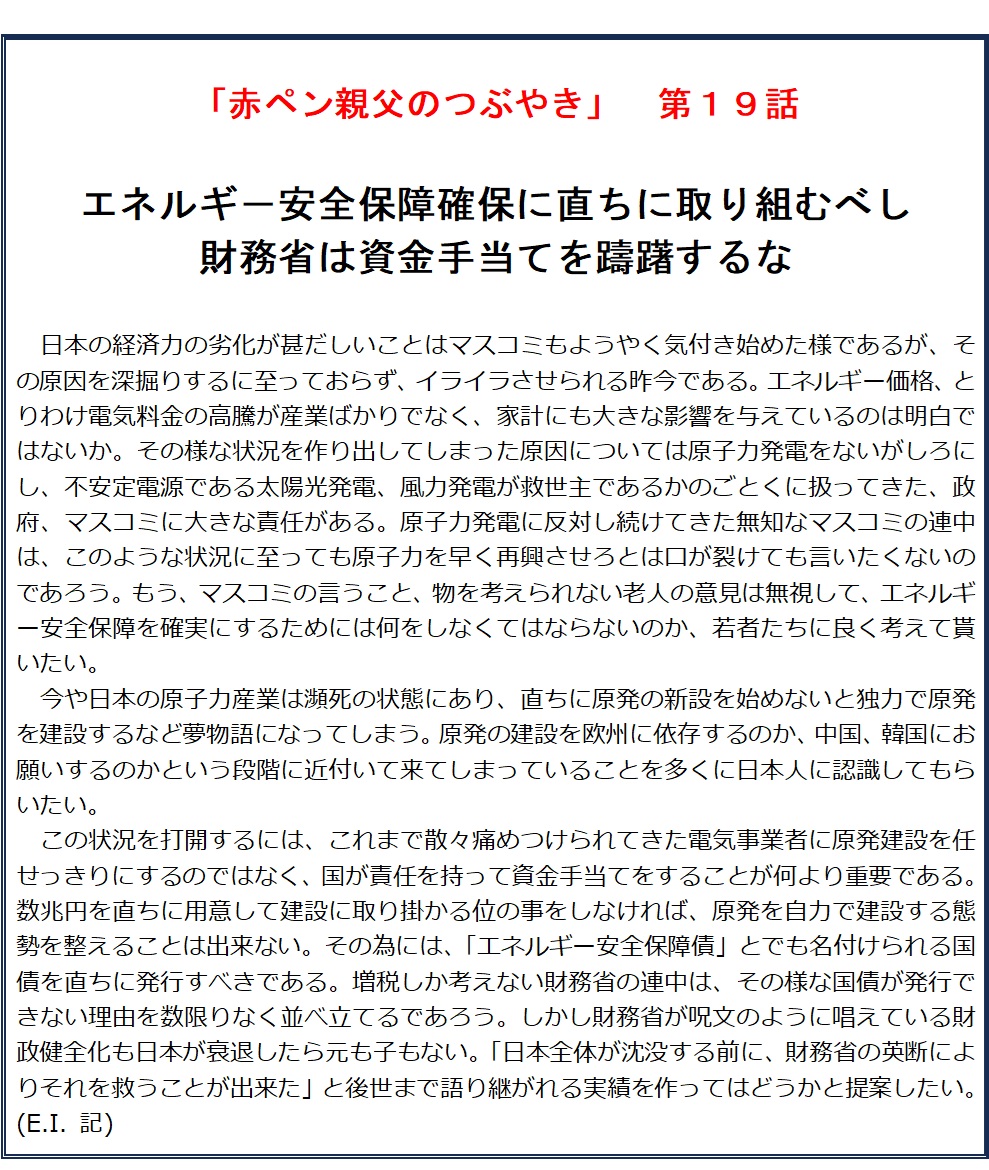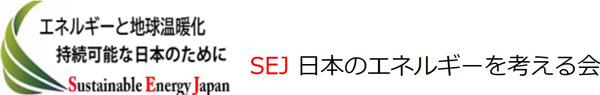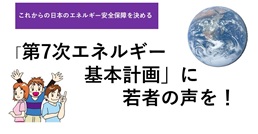 はじめに
はじめに2月18日政府は第7次エネ基を閣議決定し公表した。これまでのエネ基では原発依存度を低減するとの方針を継続していたが、今回は原子力について最大限活用すると明記したことは評価したい。第7次エネ基策定に向けて、SEJだより第41号で軽水炉を中心にこれからの新増設を進める上で、現実を直視して現状を打破して取り組むべき本質的論点を提起してきた。すなわち、原子力開発の長期目標、電力自由化環境下における事業者の開発インセンティブ、民間事業として成立する要件、サプライチェーンの維持確保策、廃炉事業の期間短縮、原子力人材の維持確保策などである。
今回のエネ基ではそれぞれのテーマについてある程度は答になっているものと、必要性や論点であることは説明されているが具体的な実現方法についてさらに踏み込むべきと思われる箇所も随所にみられ残念ながら当方の意見の趣旨は反映されなかった。
以下に第7次エネ基についてその評価とさらなる検討が必要な事項について述べる。
1 エネルギ―基本計画の総論と基本的視点について
(1) 世界のエネルギ―情勢は激しく変化しているなかで、日本としてエネルギ―安全保障の確保を図るには日本の地政学的位置づけ、経済成長との調和、国益などを考慮し日本独自の対応方針を明確に示すべきである。アメリカはパリ協定から離脱しアメリカのエネルギ―資源をフル活用する方針に切り替えたが、この動きは2050年にカーボンニュートラル達成を金科玉条としている世界趨勢の考え方に対し、将来大きな変化をあたえる可能性がある。日本も目標達成の掛け声と実態としての現実とのかい離が拡大しつつあり、エネルギ―安全保障確保の観点から幾つかのシナリオを検討して、カーボンニュートラル達成目標にとらわれない現実的に実現可能性が高いシナリオを正直に別途示す必要があるのではないか。
(2) 同日に閣議決定したGX2040ビジョンとの整合性から第7次エネ基の需給見通しの目標年度も2040年とし、原子力発電への依存については発電電力量の2割程度としているが既存原発の再稼働が実現すれば達成可能な目標となっている。この計画期間では原子力発電の新増設に対する切迫感や危機感は生じないような錯覚に陥ってしまうだろう。
今一度、あらためて日本がなぜ原子力開発を必要としているか基本計画で明らかにするべきではないか。真に日本のエネルギ―自立を実現するには、原子力政策の根幹となっている軽水炉開発、再処理事業の確立、高速炉開発への展開が必要であることに対する国民理解は既に瓦解しておりはなはだ不十分と言わざるを得ない。原子力発電の計画立案から運開までの懐妊期間は30年ないし40年かかるのが現実であり、原子力発電の計画は数十年から百年先まで見通したうえで一歩一歩着実に進めていく必要があり、原子力の開発計画は100年程度の将来を見据えた長期計画を別途作成すべきである。
(3) SEJ46号で既に再生エネルギ―に4割から5割依存する目標は日本経済を衰退に至らしめるものであり、不安定電源である太陽光発電や風力発電を主力電源として位置づけている基本計画の方針には賛同できない旨の指摘をしたところである。
基本計画では安定供給が可能な基幹電源である原子力エネルギ―を主力電源として定義するように基本計画の考え方を是正すべきと考える。
(4) 日本の原子力エネルギ―開発は閉塞感につつまれたまま推移してきた。この状態でこのまま推移すれば確実に日本の原子力開発の能力と技術を失う恐れがあり、エネルギ―安全保障の確保も危ぶまれるとの危機意識を政府、事業者、国民が一体となって認識する必要がありエネ基の総論、基本的視点で明らかにすべきではなかったか。
2 原子力政策の基本的考え方に則して具体的実現方式が基本計画に示されるべき事項
不安定(1) 日本の原子力産業の維持と技術力維持のためには、一刻も早く原子力発電の新増設着工の見通しを明らかにしその実現に取りかかるべきである。原子力産業が求める実需対策を政府が主導して提示できないかぎり原子力産業は崩壊の危機を迎えることになるだろう。原子力産業のサプライチェーンを構成している中堅、中小企業者にとっても実需が生まれるとの予想がたつことで技術、人材の維持が可能となる。
(2) 電力自由化環境のもとでこれからの原子力開発を電気事業者まかせの現状をまず大胆かつ根本的に見直し改善を図るべきである。たとえば、原子力政策実現に向けて必要な国の関与をさらに具体的に明示することは有意義な方策であろう。特にこれからの10年程度を目途に原子力開発に必要な国の投資規模を、その内訳、理由とともに明示することにより民間からの投資が呼び込めるようになる。とくに発電所建設コストが大きいことから、初期投資額に対して一定額の補助を建設国債発行で賄うことを国の政策として明示すれば建設インセンティブが高まるだろう。また、人材の維持、育成、確保についても国の投資規模を明示し実行することが求められる。
(3) 核燃料サイクルの要となる再処理事業の竣工が遅れに遅れている。規制当局のスタンスにも問題があるのではとの指摘もあり、大局的立場からの国の関与により早急に改善を図る必要があるのではないか。
(4) 今後の原子力発電の開発に既設発電所の廃炉跡地利用が提示されているが、現状では廃炉専門事業者も育成されておらず、廃炉の処分規制も整備されていないことから、跡地利用の現実化には数十年先になるとも予想される。廃炉事業期間を短縮する方策を国の主導で検討すべきと考えるが廃炉跡地だけでなく、新設立地地点の確保に向けて国が主導的役割を果たすべきである。
(5) 高レベル廃棄物処理事業を実現化するには現行の法律体系のもとでは進まないと考える。地点選定の在り方など国自らの責務を明示するため法改正が必要ではないか。
(6) (3)に関連して原子力の安全規制が科学的合理性のもとで進められているか検証が必要と考える。神棚に祭り上げてしまった規制体制を変革するには法制度を新たに定めて実行する必要がある。その上で設置法改正等の措置をとるべきではないか。(佐々木宜彦 記)
pdfはこちらから(プリント版)
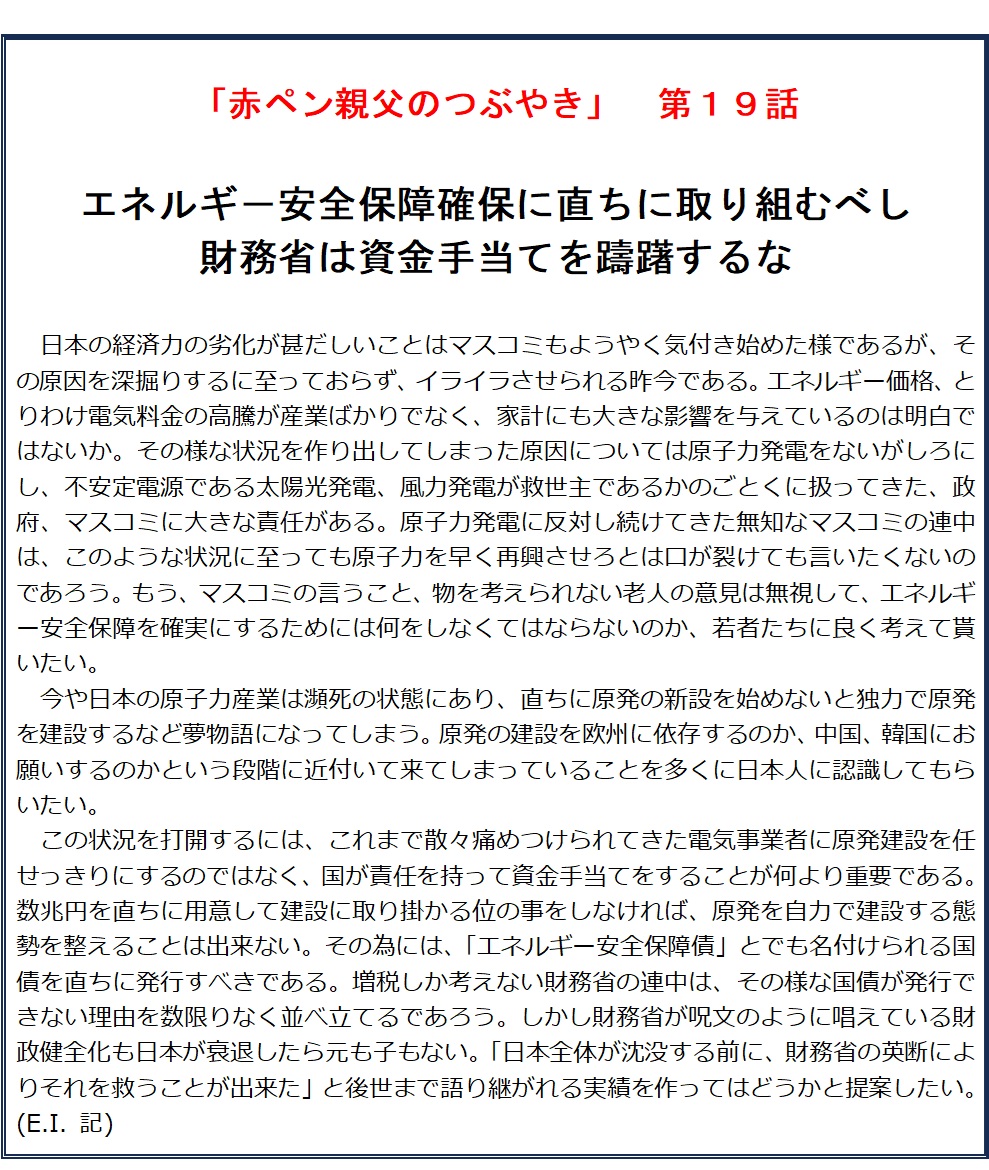
以下に第7次エネ基についてその評価とさらなる検討が必要な事項について述べる。
1 エネルギ―基本計画の総論と基本的視点について
(1) 世界のエネルギ―情勢は激しく変化しているなかで、日本としてエネルギ―安全保障の確保を図るには日本の地政学的位置づけ、経済成長との調和、国益などを考慮し日本独自の対応方針を明確に示すべきである。アメリカはパリ協定から離脱しアメリカのエネルギ―資源をフル活用する方針に切り替えたが、この動きは2050年にカーボンニュートラル達成を金科玉条としている世界趨勢の考え方に対し、将来大きな変化をあたえる可能性がある。日本も目標達成の掛け声と実態としての現実とのかい離が拡大しつつあり、エネルギ―安全保障確保の観点から幾つかのシナリオを検討して、カーボンニュートラル達成目標にとらわれない現実的に実現可能性が高いシナリオを正直に別途示す必要があるのではないか。
(2) 同日に閣議決定したGX2040ビジョンとの整合性から第7次エネ基の需給見通しの目標年度も2040年とし、原子力発電への依存については発電電力量の2割程度としているが既存原発の再稼働が実現すれば達成可能な目標となっている。この計画期間では原子力発電の新増設に対する切迫感や危機感は生じないような錯覚に陥ってしまうだろう。
今一度、あらためて日本がなぜ原子力開発を必要としているか基本計画で明らかにするべきではないか。真に日本のエネルギ―自立を実現するには、原子力政策の根幹となっている軽水炉開発、再処理事業の確立、高速炉開発への展開が必要であることに対する国民理解は既に瓦解しておりはなはだ不十分と言わざるを得ない。原子力発電の計画立案から運開までの懐妊期間は30年ないし40年かかるのが現実であり、原子力発電の計画は数十年から百年先まで見通したうえで一歩一歩着実に進めていく必要があり、原子力の開発計画は100年程度の将来を見据えた長期計画を別途作成すべきである。
(3) SEJ46号で既に再生エネルギ―に4割から5割依存する目標は日本経済を衰退に至らしめるものであり、不安定電源である太陽光発電や風力発電を主力電源として位置づけている基本計画の方針には賛同できない旨の指摘をしたところである。
基本計画では安定供給が可能な基幹電源である原子力エネルギ―を主力電源として定義するように基本計画の考え方を是正すべきと考える。
(4) 日本の原子力エネルギ―開発は閉塞感につつまれたまま推移してきた。この状態でこのまま推移すれば確実に日本の原子力開発の能力と技術を失う恐れがあり、エネルギ―安全保障の確保も危ぶまれるとの危機意識を政府、事業者、国民が一体となって認識する必要がありエネ基の総論、基本的視点で明らかにすべきではなかったか。
2 原子力政策の基本的考え方に則して具体的実現方式が基本計画に示されるべき事項
不安定(1) 日本の原子力産業の維持と技術力維持のためには、一刻も早く原子力発電の新増設着工の見通しを明らかにしその実現に取りかかるべきである。原子力産業が求める実需対策を政府が主導して提示できないかぎり原子力産業は崩壊の危機を迎えることになるだろう。原子力産業のサプライチェーンを構成している中堅、中小企業者にとっても実需が生まれるとの予想がたつことで技術、人材の維持が可能となる。
(2) 電力自由化環境のもとでこれからの原子力開発を電気事業者まかせの現状をまず大胆かつ根本的に見直し改善を図るべきである。たとえば、原子力政策実現に向けて必要な国の関与をさらに具体的に明示することは有意義な方策であろう。特にこれからの10年程度を目途に原子力開発に必要な国の投資規模を、その内訳、理由とともに明示することにより民間からの投資が呼び込めるようになる。とくに発電所建設コストが大きいことから、初期投資額に対して一定額の補助を建設国債発行で賄うことを国の政策として明示すれば建設インセンティブが高まるだろう。また、人材の維持、育成、確保についても国の投資規模を明示し実行することが求められる。
(3) 核燃料サイクルの要となる再処理事業の竣工が遅れに遅れている。規制当局のスタンスにも問題があるのではとの指摘もあり、大局的立場からの国の関与により早急に改善を図る必要があるのではないか。
(4) 今後の原子力発電の開発に既設発電所の廃炉跡地利用が提示されているが、現状では廃炉専門事業者も育成されておらず、廃炉の処分規制も整備されていないことから、跡地利用の現実化には数十年先になるとも予想される。廃炉事業期間を短縮する方策を国の主導で検討すべきと考えるが廃炉跡地だけでなく、新設立地地点の確保に向けて国が主導的役割を果たすべきである。
(5) 高レベル廃棄物処理事業を実現化するには現行の法律体系のもとでは進まないと考える。地点選定の在り方など国自らの責務を明示するため法改正が必要ではないか。
(6) (3)に関連して原子力の安全規制が科学的合理性のもとで進められているか検証が必要と考える。神棚に祭り上げてしまった規制体制を変革するには法制度を新たに定めて実行する必要がある。その上で設置法改正等の措置をとるべきではないか。(佐々木宜彦 記)
pdfはこちらから(プリント版)
ここから赤ペン親父つぶやきコーナー